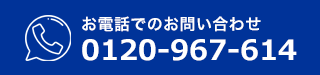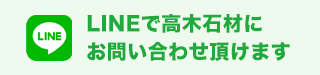お知らせ
お彼岸を清々しく迎えるために。石のプロ-高木石材店(犬山市)が教えるお墓掃除のコツ
2月に入り、暦の上ではまもなく「立春」を迎えます。
とはいえ、まだまだ風は冷たく、春の暖かさが待ち遠しい日々ですね。
さて、この寒さが和らいだ先にやってくるのが「春のお彼岸」です。
2026年の春のお彼岸は、3月17日(火)から23日(月)までの7日間。
「まだ先のこと」と感じるかもしれませんが、実は2月の今からお掃除の計画を立てておくと、お彼岸当日にゆとりを持ってご先祖様と穏やかな時間を過ごすことができます。
今回は、春を清々しく迎えるための「お墓掃除の深掘りガイド」をお届けします。

1. お掃除は「上から下へ」が鉄則
お墓掃除を効率よく、かつ丁寧に進めるための基本は、家のお掃除と同じく高いところから低いところへと順番に洗っていくことです。
まずは敷地内の落ち葉を掃き、冬の間に伸びた枯れ草を抜いて周囲を整えることから始めましょう。
土台が綺麗になったら、次はいよいよ石塔(お墓本体)に取りかかりますが、ここでいきなり雑巾でこするのは禁物です。
石の表面には目に見えない細かな砂やホコリが付着しており、そのまま拭くと砂がヤスリのような役割をして石を傷つけてしまうからです。
墓石を洗う前にバケツの水をたっぷりと使い、上から順に汚れを洗い流してあげてください。
水でしっかり汚れを浮かせてから、柔らかいスポンジや布で優しく撫でるように洗うのが、石を長持ちさせる秘訣です。
2. 「洗剤」は使わないのがプロの常識
意外と知られていないのが、「お墓に家庭用洗剤は禁物」という点です。
市販の洗剤に含まれる成分は、石に染み込んでシミになったり、変色の原因になったりすることがあります。
基本は「水洗い」のみで、石の艶を守るためにも、柔らかいスポンジや布で優しく撫でるように洗うのがベストです。
3. 文字の彫刻部分は「使い古しの歯ブラシ」で
お墓の中で最も汚れが溜まりやすいのが、家紋や苗字が彫られた文字の部分。ここは雑巾では届きません。
使い古した柔らかい歯ブラシを使って、優しく円を描くように汚れを掻き出してください。
ここが綺麗になると、お墓全体の表情がパッと明るく引き締まります。
4. 仕上げの「乾拭き」が劇的な差を生む
ここがプロのおすすめする最大のポイントです。 水洗いの後、そのまま自然乾燥させていませんか?
最後に「乾いた布で水気を拭き取る」だけで、その後の美しさが劇的に変わります。
水気が残っていると、そこにホコリが付着しやすく、水垢(水滴の跡)の原因になります。最後に優しく拭き上げることで、石本来の艶が蘇ります。
5. 冬の間にダメージはありませんでしたか?
2月にお墓を確認するメリットがもう一つあります。それは「冬の間のダメージ」をチェックできることです。
厳しい寒さで凍結を繰り返すと、石の継ぎ目(目地)が傷んだり、小さなひび割れが広がったりすることがあります。
お掃除のついでに、「目地が剥がれていないか」「石がズレていないか」をぜひ確認してみてください。
困ったときは、プロの力を頼ってください
丁寧にお掃除をしても、「どうしても落ちない頑固なシミがある」「高いところまで手が届かない」といったお悩みが出てくるかもしれません。
お墓は家族の歴史を刻む大切な場所。もしご自身でのケアに限界を感じたら、お気軽に高木石材店へご相談ください。
お彼岸に向けて、プロによるクリーニングや補修など、最適なメンテナンスをご提案させていただきます。
今年の春は、ピカピカになったお墓で、心穏やかにご先祖様へ近況報告をしてみませんか?
お墓の色入れ直しとは?費用・効果・施工方法を高木石材店(犬山市)が解説します
お墓の色入れ直しで、文字と想いをもう一度くっきりと
お墓の文字や家紋の色が薄くなってきたと感じたことはありませんか?
長年の風雨や紫外線によって、文字の色は少しずつ劣化していきます。
今回は、「お墓の色入れ直し(色入れ)」について、
実際の施工写真を交えながらご紹介します。
お墓の「色入れ直し」とは?

お墓の色入れ直しとは、
墓石に彫られた文字や家紋に新しく色を入れ直すメンテナンス作業です。
・文字が読みづらくなった
・色が剥がれてまだらになっている
・全体的に古く見える
このような状態のお墓でも、色入れを行うことで印象が大きく変わります。
色入れ直しをすると、ここまで変わります

色入れ直しを行うと、
・文字がはっきりして読みやすくなる
・墓石全体が明るく、きれいな印象になる
・「きちんと手入れされているお墓」に見える
といった変化があります。
「色を入れ直しただけなのに、新しいお墓みたいですね」
とお声をいただくことも少なくありません。
施工の流れ(色入れ直し)

色入れ直しは、以下のような手順で行います。
1. 文字部分の汚れ・古い塗料を丁寧に清掃
2. 専用の塗料を使い、文字の中に色を入れる
3. はみ出しやムラを調整し、仕上げ
細かい作業のため、仕上がりの美しさは職人の技術が重要です。
色入れ直しのおすすめタイミング

以下のようなタイミングでのご相談が多いです。
・お盆・お彼岸前
・墓参りの際に文字の薄さが気になったとき
・彫刻追加や墓石クリーニングと一緒に
「今すぐ直さないといけない」というより、
気になった時がベストなタイミングです。
色入れ直しで、お墓への想いを形に
色入れ直しは、見た目をきれいにするだけでなく、
ご先祖様を大切に思う気持ちを形にするお手入れでもあります。
・文字が読みやすくなる
・お墓が明るくなる
・お参りする気持ちも自然と整う
お墓の文字が少しでも気になっている方は、
一度、色入れ直しをご検討されてみてはいかがでしょうか。
お墓が遠方にあり気軽に行けなくなってしまったら、高木石材店(犬山市)にご相談ください
お墓参りに行けないとき、選択肢はひとつじゃありません
「お墓が遠くて、なかなか行けなくなった」
こうしたご相談は、ここ数年で確実に増えています。
仕事や生活拠点が変わったり、年齢を重ねて移動が負担になったり。
理由は人それぞれですが、多くの方が共通して口にされるのが
「行けなくなってしまって、申し訳ない気がする」という言葉です。
けれど、お墓との向き合い方は、
頻繁に通えているかどうかだけで決まるものではありません。

遠方にあるお墓が、気がかりになる理由
遠方にお墓がある場合、日常生活の中でふと気になる瞬間があります。
最近お墓の様子はどうだろうか、
雑草が伸びていないだろうか、
お寺や霊園に迷惑をかけていないだろうか。
今すぐ困っているわけではないけれど、
「このままでいいのだろうか」という小さな引っかかりが、
ずっと心の中に残っている状態です。
多くの方は、その気持ちを抱えたまま、
特に行動を起こさず時間だけが過ぎていきます。

無理をして通い続けることが、正解とは限りません
遠方でも「できるだけ通わなければ」と考え、
体力や時間に無理をしながらお墓参りを続けている方もいらっしゃいます。
もちろん、それが負担になっていなければ問題ありません。
ただ、気持ちのどこかで「しんどい」と感じているのであれば、
向き合い方を見直すタイミングかもしれません。
お墓との関係は、
生活環境や家族構成の変化に合わせて変わっていってもいいものです。
お墓の移転という考え方
遠方のお墓について考える中で、
「お墓の移転」という選択肢に触れる方も増えています。
移転と聞くと、
ご先祖をないがしろにしているような気がしたり、
何か悪いことをしているように感じたりする方も少なくありません。
しかし実際には、
これからも無理なく手を合わせていくための前向きな選択として
移転を考えられるケースが多くあります。
自宅から通いやすい場所に移すことで、
お墓参りが「特別な用事」ではなく、
自然な日常の延長になることもあります。
移転を考えるきっかけに、決まった正解はありません
お墓の移転は、
「今すぐ決めなければならないもの」ではありません。
体力的な変化や、家族との話し合い、
ふとした不安や違和感がきっかけになることがほとんどです。
「まだ早いかもしれない」
「でも、いずれは考えなければ」
その間で揺れている状態も、決して間違いではありません。
高木石材店では、まず“話を整理する”ところから
高木石材店では、
遠方にあるお墓についてのご相談を多くお受けしています。
必ずしも移転をおすすめするわけではなく、
今のままでも問題がないのか、
将来的にどんな選択肢があるのかを一緒に整理するところから始めています。
お墓の移転を含め、
今後の向き合い方を落ち着いて考えるための相談先として、
気軽に声をかけていただければと思います。
行けなくなったからこそ、考えていいお墓のこと
お墓に行けなくなったことは、
後ろめたく感じる必要のあることではありません。
今の生活の中で、
どんな形がいちばん自然なのかを考えることが、
これから先のお墓との付き合い方につながっていきます。

お墓に行けないと悩んでいませんか?石のプロ「高木石材店(犬山市)」のお墓参り代行が選ばれる理由
「進学や就職で地元を離れ、お墓参りになかなか行けない」 「高齢になり、お墓掃除などの重労働が難しくなってきた」 「仕事や育児が忙しく、気づけば最後のお墓参りから時間が経ってしまった…」
愛知県犬山市の高木石材店です。 当店には、このようなお悩みのご相談が年々増えています。
ご先祖様を大切にしたい気持ちはあるのに、物理的な理由でお参りできないことに対し、「申し訳ない」「お墓が荒れていないか心配」と、心のどこかで罪悪感を感じている方は少なくありません。
今回は、そんなお悩みを解決するための選択肢、高木石材店のお墓参り代行サービスについてご紹介します。

1. お墓参り代行は「手抜き」ではありません
「お墓参りを人に頼むなんて、バチが当たるのでは?」 以前はそんな風に考える方もいらっしゃいました。しかし、現在はライフスタイルの変化により、お墓参り代行は「お墓を大切にするための前向きな手段」として定着してきています。
何年も放置して雑草だらけになってしまうよりも、人の手を借りてでも綺麗に保たれている方が、ご先祖様もきっと喜んでくれるはずです。
2. 一般の代行業者とここが違う!「石材店」に頼むメリット
インターネットで検索すると、便利屋や清掃業者の代行サービスも多く見つかります。しかし、私たち高木石材店のような「お墓のプロ」にお任せいただくことには、大きなメリットがあります。
① 石の状態を「プロの目」でチェックできる
私たちは昭和51年創業の石材店です。お掃除をするだけでなく、
・「石にヒビが入っていないか」
・「目地(石のつなぎ目)が切れていないか」
・「地震などで傾きが生じていないか」
など、専門家ならではの視点で墓石の健康診断も同時に行います。これは一般的な清掃業者では気づけないポイントです。
② 正しい知識での丁寧なクリーニング
石の種類や状態に合わせ、墓石を傷つけない適切な方法で丁寧に汚れを落とします。大切な故人様が眠る場所だからこそ、私たちはまごころを込めて手作業を行います。
3. お墓参り代行サービスの内容
当店のサービスは、ただ掃除をするだけではありません。ご家族様に代わって、しっかりとお参りをさせていただきます。
1. 合掌・礼拝:作業前に、失礼のないようご挨拶をします。
2. 清掃作業:草取り、ゴミ拾い、墓石の水洗い、水鉢・花立の清掃など。
3. お供え:お水、お花、お線香をお供えします。
4. 写真付き報告書:作業前と作業後(ビフォーアフター)の写真を撮影し、LINEやメール、郵送にてご報告します。
遠くにいても、きれいになったお墓の写真を見ることで、「やっとちゃんとお参りできた」と心のつかえが取れた、とおっしゃるお客様も多いです。
4. 対応エリアについて
高木石材店では、地元に密着した迅速な対応を心がけております。
【主な対応エリア】
愛知県犬山市、扶桑町、大口町、江南市 岐阜県可児市、坂祝町、各務原市(鵜沼地区)など
※上記以外の地域でも、近隣であれば対応可能な場合がございます。まずはお気軽にご相談ください。
■最後に
お墓のことは気になっているけれど、どうしても行けない。そんな時は、無理をせず私たちプロを頼ってください。 あなたに代わって、責任を持って大切なお墓をお守りします。
1回のみのスポット利用はもちろん、年数回の定期プランもご用意しております。
まずは「お墓の場所」と「気になっていること」を、お気軽にお問い合わせください。
ペットのお墓の選び方や供養の方法について高木石材店(犬山市)ができることを解説します
近年、「ペットも家族だから、きちんとお墓を作ってあげたい」というお声を多くいただくようになりました。
高木石材店でも、お墓の相談は人のお墓だけでなく、ペットのお墓についてのお問い合わせが年々増えています。
今回は、ペットのお墓の選び方・供養の方法・石材店としてできることを、分かりやすくまとめました。
ペットのお墓を考える人が増えている理由
ペットの存在が「家族そのもの」になっている現在、
・生前から一緒に過ごした証を形として残したい
・お庭で供養したい
・自分たちのお墓の近くに眠らせたい
など、「家族として弔う」という考え方が一般的になってきています。
また、単なる記念碑とは違い、
「きちんとした石材で、長く残る形にしたい」
というご希望も多いのが特徴です。
ペットのお墓にはどんな種類がある?
ペットのお墓といっても、希望や環境によりさまざまな形が選べます。
1) 自宅のお庭に設置するタイプ
一番選ばれている方法です。
敷地内に安置するため、常に近くで手を合わせられるという安心感があります。
・小型の墓石
・プレート型
・モニュメント型
サイズやデザインも自由度が高く、飼い主さまの想いを形にしやすい方法です。
※自治体によって埋葬ルールが異なるため、事前確認が必要です。
2) 人のお墓と同じ敷地に建立するタイプ
「自分たちが入るお墓に一緒に眠らせたい」
というお考えの方もいらっしゃいます。
宗派や霊園によってはペット埋葬を許可していないところもありますが、
近年は【ペット共葬】が可能な墓地や霊園が増加しています。
高木石材店では、霊園ごとの規定を調べ、
ペット共葬が可能かどうかの確認もサポートしています。
3) 合同供養・納骨堂を利用するタイプ
個別のお墓を持たない方法として、動物霊園や寺院での合同供養があります。
・費用を抑えられる
・維持管理の負担が少ない
・宗教的な儀式にのっとって供養できる
などのメリットがあります。
ペットのお墓に使われる石とデザイン
ペットのお墓でも、人のお墓と同じように
耐久性の高い御影石(花崗岩)が主流です。
高木石材店では、
「小さくても美しく長持ちする石」
「庭に溶け込む自然な石」
など、用途に合った石をご提案しています。
人気のデザイン例
・足跡マークを刻む
・シルエットの彫刻(犬・猫・鳥・うさぎ など)
・生前の名前や性格に合わせたモチーフ
・写真彫刻
「シンプルに名前だけ刻みたい」という方もいれば、
「写真を刻んで、いつも見守っていてほしい」という方もおられます。
ペットのお墓を作るときの流れ
1) ご相談・ヒアリング
種類・サイズ・予算・設置場所などを伺います。
2) デザインと石材の選定
イメージに合わせてご提案。
3) お見積り
明確な料金で提示します。
4) 施工・設置
石材専門の職人が丁寧に仕上げます。
5) アフターサポート
メンテナンスや追加彫刻も可能です。
高木石材店は「石のプロ」として、
小さなお墓でも品質を落とさず、長く残せるものをお作りします。
家族としての「ありがとう」を形に
ペットのお墓は、
「悲しみを癒すための場所」であると同時に、
「一緒に生きた証を残す場所」でもあります。
どんな形を選んでも、
大切なのは「想いが込もっていること」。
高木石材店は、
飼い主さまの気持ちに寄り添いながら、
ペットへの「ありがとう」を形にするお手伝いをさせていただきます。
墓じまいについて、流れ・費用・供養先を高木石材店(犬山市)がわかりやすく解説します!

少子高齢化やライフスタイルの変化により、近年「墓じまい」を選択する人が増えています。
墓じまいはお墓を撤去し、ご遺骨を別の供養先へ移すことを指しますが、実際には多くの手順が必要です。
ここでは、高木石材店が実際に行っている流れをもとに、わかりやすく解説します。
■ 墓じまいとは
墓じまいとは、現在のお墓を撤去し、遺骨を別の場所へ移す(改葬する)ことです。
維持が難しい場合や、将来の管理を見据えて検討されることが多く、永代供養墓・納骨堂・新しいお墓など、供養先の選択肢も広がっています。
■ 墓じまいが増えている理由
・お墓のある地域から離れて暮らす人が増えた
・継承者がいない、または負担をかけたくない
・管理費や維持の問題
・将来の供養方法を見直したい
背景は家庭によってさまざまですが、【お墓の維持が現実的かどうか】を基準に検討されるケースが多く見られます。
■ 墓じまいの基本的な流れ
① 閉眼供養(魂抜き)
お墓を撤去する前に、僧侶による読経を行い、墓石の魂を抜く儀式です。
墓じまいの最初のステップとなります。
② お墓の解体・撤去
石材店が専門の機材を使い、墓石を安全に解体します。
基礎のコンクリートの撤去や更地化まで行う場合もあります。
③ 遺骨の取り出し
ご遺骨を丁寧に取り出し、新しい供養先へ移す準備をします。
④ 改葬手続き(行政手続き)
遺骨を別の場所へ移すには、市町村で「改葬許可証」を取得する必要があります。
必要書類や手順は自治体ごとに異なりますが、高木石材店でもサポート可能です。
⑤ 新しい供養先へ納骨
永代供養墓、納骨堂、新しい墓地など、ご家庭に合った場所へ納骨します。
■ 供養先の選択肢
墓じまいにあたって、遺骨の移動先を決めることが重要です。
・永代供養墓
寺院や霊園が永続的に供養してくれるため、継承者が不要。
・納骨堂
屋内型で管理しやすく、アクセスが良い場合が多い。
・新しいお墓へ改葬
自宅近くの墓地へ移し、管理をしやすくするケース。
高木石材店では地域の寺院・霊園との連携実績があり、ご希望に合わせた提案が可能です。
■ 墓じまいを進める際の注意点
・事前に墓地管理者へ連絡し、規定や撤去方法を確認する
・親族間での合意形成を行う
・改葬先の受け入れ証明を準備する
・撤去費用(石の大きさ・立地条件で変動)を見積もっておく
事前準備をしっかり行うことで、スムーズに墓じまいを進められます。
■ 高木石材店が選ばれる理由
・墓じまいの多数の施工実績
・土葬墓や特殊な環境にも対応
・寺院・霊園との連携によるスムーズな改葬
・工程説明や行政手続きサポートが明確
地域密着型の石材店として、「わかりにくい部分をしっかり説明する」を大切にしています。
■ まずは相談から
墓じまいは一度行うと元に戻せないため、慎重に進める必要があります。
「具体的には決めていないが話だけ聞きたい」
「自分のケースでどれくらい費用がかかるのか知りたい」
こうしたお問い合わせにも対応しています。
状況に合わせて最適な進め方をご提案しますので、まずはお気軽に高木石材店までご相談ください。
お墓のリフォームとは?費用や内容を高木石材店(犬山市)がわかりやすく解説
長い年月を経て建てられたお墓は、風雨や地震などの影響で少しずつ劣化していきます。
「お墓が傾いてきた」「石が欠けている」「彫刻が薄くなって読めない」——そんな時に検討したいのが“お墓のリフォーム”です。
建て替えとは異なり、今あるお墓を活かしながら修繕・再生する方法で、ご先祖さまへの想いをそのままに、美しく整えることができます。
高木石材店がお手伝いできる主なリフォーム内容
高木石材店では、お墓の状態やお客様のご希望に合わせて、様々なリフォームを行っています。
・墓石の磨き直し・再研磨
経年によるくすみや水垢を取り除き、新品のような輝きを取り戻します。

・傾きやズレの修正
地盤の沈下や地震の影響による傾きを修正し、再び安全で美しい状態に。

・目地補修・耐震施工
石と石の間の目地が劣化している場合は補修を行い、地震に強い構造へ改善します。

・花立・香炉・外柵の交換
劣化した金具や部材を新しくし、お参りしやすい環境を整えます。

・戒名・法名の追加彫刻
新たに法要を終えた方の戒名を追加彫刻し、これまでのお墓をそのまま引き継ぎます。

・墓誌・敷地内の整備
雑草対策や玉砂利の入れ替えなど、見た目とお手入れのしやすさも向上させます。

リフォームの流れ
1. 現地調査・ご相談(無料)
お墓の現状を確認し、ご希望やご予算を伺います。
2. お見積り・ご提案
修繕内容や工期を明確にし、最適なプランをご提案します。
3. 施工・仕上げ確認
熟練の石職人が丁寧に作業し、仕上がりをお客様にご確認いただきます。
工事期間は内容にもよりますが、部分修理であれば数日〜1週間ほどで完了します。
費用の目安
お墓の状態や規模によって異なりますが、
・傾き修正・目地補修などの部分リフォーム:数万円〜
・全体磨きや外柵の修繕を含む総合リフォーム:20〜40万円前後
が一般的な目安です。
高木石材店では、現地調査とお見積りを無料で実施していますので、まずはお気軽にご相談ください。
大切なお墓を、これからも美しく守るために
お墓はご先祖さまとの絆をつなぐ大切な場所。
長年の風雨で傷んだお墓も、適切なリフォームで驚くほど美しくよみがえります。
高木石材店では、石の状態を見極めながら、一基一基丁寧に修繕いたします。
「建て替えるほどではないけれど、気になっている箇所がある」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
お墓の費用、どれくらいかかるかを?お墓のプロである高木石材店(犬山市)が解説します
●墓石を建てる費用(新規建立)
お墓を新しく建てる場合、費用の中心となるのが墓石代と施工費です。
・墓石代:使用する石の種類・品質・産地によって価格が大きく異なります。
高木石材店で取り扱っている墓石も55万円のものから220万円のものまで幅広く取り揃えております。
・施工費・基礎工事費:お墓の形や区画の大きさによって変わります。
高木石材店では、ご予算に応じて墓石のデザインや石種などの最適なご提案をいたします。
現地確認・お見積りは無料です。
●合祀(ごうし)の費用
近年、後継ぎの問題や管理負担の軽減から合祀(合同供養)を選ばれる方も増えています。
合祀とは、複数のご遺骨をひとつのお墓や納骨堂にまとめて供養する方法です。
・費用の目安:1体あたり 3万円〜10万円程度
永代供養料を含む場合は10万〜30万円程度が一般的です。
・費用に含まれるもの:納骨手続き・供養料・永代管理料など
高木石材店では、ご希望に合わせて地域の寺院や霊園の合祀プランもご案内可能です。

●お墓のリフォーム費用
お墓は年月とともに風雨で汚れや劣化が進みます。
クリーニングや補修、彫刻の追加、外柵の修繕などを行うことで、美しさと安全性を保てます。
主なリフォーム内容と費用目安:
お墓参り代行(簡易清掃):¥19,800/回
汚れ落とし:¥33,000〜
高圧洗浄(代行セット):¥22,000〜
文字の色入れ直し:¥15,000〜
外回り修理(花立て等):¥22,000〜(要見積)
文字・名入れ:¥44,000〜
定期的な清掃や点検も承っております。
「古くなったけれど建て替えるほどでは…」という場合も、まずはご相談ください。

●お墓の移転(引っ越し)費用
遠方への引っ越しや墓地の閉鎖などで、お墓を別の場所へ移すケースもあります。
これを「改葬(かいそう)」と呼び、行政手続きと専門業者による施工が必要です。
主な費用項目:
・解体・撤去(標準墓石):約¥80,000〜
・運搬費:距離や所在地によって変動(別途見積)
・再設置・据付:石材と施工条件で数十万円〜
高木石材店では、改葬の申請手続きサポートから運搬・再設置まで一括対応いたします。
「どこから手をつければいいかわからない」という方も安心してご相談ください。
●まとめ
公開価格は目安となっておりますので、最終見積りは現地調査のうえで決定いたします。
見積りを依頼する際は、下記をご確認いただけますとスムーズです。
・ご希望の石種やデザイン(参考画像や掲載ページへのリンク)
・現地の写真(区画・周辺状況・出入り口)
・ご希望の納期、予算
高木石材店では、墓石の建立から合祀、リフォーム、移転までご家族の想いを大切にしたご提案を行っております。
お見積り・現地調査は無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください。
お墓の撤去とその後の供養について、高木石材店(犬山市)が解説します
お墓の撤去とは
墓じまいを行う際、まず必要なのが「お墓の撤去・解体工事」です。
墓石を取り外し、基礎を解体し、更地に戻す作業を行います。
お墓の大きさや立地条件によって作業工程や費用は変わりますが、石材店が安全に工事を進めますのでご安心ください。
撤去前に行う「閉眼供養」
撤去に入る前に欠かせないのが「閉眼供養(魂抜き)」です。
お墓には故人の魂が宿っていると考えられるため、僧侶に読経をお願いし、仏様へとお還しする儀式を行います。
この供養を経てから撤去することで、ご先祖さまへの礼を尽くすことができます。
撤去後のご遺骨の供養先
お墓を撤去した後、ご遺骨は新しい場所へと移します。代表的な選択肢は次の通りです。
・永代供養墓:寺院や霊園が永続的に供養してくれる合祀墓。
・納骨堂:屋内にて個別に安置するスタイル。
・新しいお墓への改葬:別の場所に新しくお墓を建てる場合。
ご家族のご事情や将来の継承を考慮して選ぶことが大切です。
撤去費用の目安
お墓の撤去費用は、一般的に 1㎡あたり10万~20万円前後 が相場といわれています。
ただし、お墓の大きさや石材の種類、立地条件(山間部や搬出の難しい場所など)によって変動するため、必ず見積もりを取ることをおすすめします。
高木石材店ができること
高木石材店では、
・閉眼供養(魂抜き)の手配
・撤去・解体工事
・新しい供養先への納骨サポート
をトータルでサポートしています。
「お墓を撤去した後、どうしたらいいのか分からない…」という方も、安心してご相談ください。
最後に
墓じまいは「撤去」と「その後の供養」を正しく行うことが大切です。
供養をきちんと行うことで、ご先祖さまへの感謝の気持ちを形にできます。
費用の目安はありますが、お墓の条件によって変動するため、まずは信頼できる石材店にご相談ください。